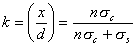 . . . . . . . . (1)
. . . . . . . . (1)矩形梁の計算は、鉄筋コンクリートの設計で最も基礎的な計算の一つです。複雑なコンクリート断面の設計を進めるとき、最初に単鉄筋コンクリート矩形断面としての予備計算をしておいて、そのデータを基にして細部を調整し、応力計算で検証するのが実践的な設計作業です。例えば次節1.3で説明する複鉄筋矩形断面の設計もそうです。T型断面の梁は、矩形断面の引張り側のコンクリートが計算には入りませんので、その部分の幅を狭くした構造と置くことができるからです。
単鉄筋コンクリート矩形梁の設計は、梁の幅bを仮定して、設計曲げモーメントMに抵抗できるように梁の有効高さdと引張鉄筋の所要断面積Asとを計算します。橋梁などの床版の設計も矩形梁として設計しますが、その場合の幅は、単位幅1m=100cmで計算します。そのため、矩形梁の設計曲げモーメントは、M/bの形で式の中で応用するのが普通です。梁の実際高さhは、有効高さdに加えて、鉄筋径の1/2と、梁下面の鉄筋のカブリを含めた分だけ高くなります。断面設計の数学的な計算条件と求めたい解とは次のようになります。ただし、説明は重力単位です。
|
計算条件: 計算結果: |
理論計算式には幾つかのパラメータが現れますが、実用的に重要な数値には、中立軸の位置xと有効高さdとの比k =(x/d)があります。この比は、コンクリートと鉄筋の応力が丁度許容応力になる条件を代入すると一意に決まる定数です。
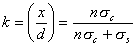 . . . . . . . . (1)
. . . . . . . . (1)
この比の条件を満たすようすると、鉄筋量Asは、コンクリートの有効高さdに比例した大きさになります。そこで、与えられた曲げモーメントに対して鉄筋が丁度許容応力になるようにdを求めます。その計算式は、下のようになります。
 . . . . . . . . (2)
. . . . . . . . (2)
ただし
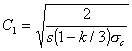 . . . . . . . . (3)
. . . . . . . . (3)
ここで、パラメータとしてjを使うことがあります。これは圧縮側コンクリートの合力の作用位置と引張鉄筋との間隔がjdで与えられるとします。この間隔は、コンクリート断面の剪断応力を計算する場合にも用いられます。
 . . . . . . . . (4)
. . . . . . . . (4)
所要鉄筋量は下の式で計算されます。
 . . . . . . . . (5)
. . . . . . . . (5)
ただし . . . . . . . . (6)
. . . . . . . . (6)
上の式-1〜式-6は、断面算定を目的としたものです。パソコンが利用できなかった時代の設計ハンドブックには、上記の式と共にk、j、p、C1、C2を含む各種のパラメータの数表やモノグラフが付いていました。定数記号の表し方も、参考文献によって違いがあります。上の記号表記は、吉田徳次郎[1]に則りました。パソコンで簡単に計算ができるようになって、計算原理が省略されることが多くなりましたので、手計算で数値を確かめる目的もあって、成るべく式の原形を載せました。
単鉄筋コンクリート矩形梁の設計計算において、有効高さdと所要鉄筋断面積Asとの理論値が求まれば、実際断面は、この値よりもやや大きめの数値を採用します。寸法を変えると、設計計算の仮定であった許容応力を基にした応力分布が変わります。考え方としては二つの選択肢に分けて考えるのがよいでしょう。一つは、dを変えないでAsを増やすこと、もう一つはAsをそのままにしてdを増加させることです。両方変えたいときは二度に分けて考えればよいでしょう。Asを増加させることはpを増加させることになり、鉄筋の応力減少の方に効果があります。dを増すのは、結果的にpを減らすことになるのですが、コンクリートの応力を下げる方に利いてきます。矩形断面の設計値を議論するとき、実用的にはコンクリート断面との比で表わした鉄筋比p = As/bdで判断します。pは、小さ過ぎても大き過ぎても実用的ではありません。
上の諸式は応力精査の場合にも応用しますので、数値的な性質を要約しておきます。コンクリートと鉄筋の許容応力度σcaとσsaとは必須の定数です。1950年頃の設計では、σca= 60 kg/cm2、σsa= 1200 kg/cm2程度でした。式(1)のkと式(6)のpは、コンクリートと鉄筋の応力の比だけに関係し、断面設計の場合には、k = 0.429、p = 1.07%です。実際断面では、計算で必要な鉄筋量の他に直交する方向の配力鉄筋などの余分な鉄筋を使用しますので、計算で必要な鉄筋量は2%以下が普通です。有効高さdの計算に使うパラメータC1は、許容応力の平方根に逆比例します。つまり、許容応力が高く取れれば桁高を相対的に低くできます。この場合、重力単位を使えばC1 = 0.301ですが、SI単位系を使うと別の数値になります。
ところで、上の諸式は、前の1.1節、表3の最上段(1)の計算を目的としたものです。現実的な設計要望では、例えば、桁高dを決めれば幅bがどれだけ必要か(2);bとdとが与えられ、断面を単鉄筋とし設計するならば抵抗モーメントはどれだけになるか(4);などがあります。また、鉄筋断面積があらかじめ与えられていて、単鉄筋断面としての抵抗モーメントを知りたい(7)〜(9)などの要望もあります。これらは先の諸式の応用で計算できますが、鉄筋量p = As/bdが変われば中立軸の位置も変わります。応力度計算に使うには、別の式が必要です。pが変われば中立軸の位置を表すパラメータkも変わりますので、pからkを求める計算式を示します。
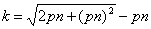 . . . . . . . . (7)
. . . . . . . . (7)
曲げモーメントに対して生じるコンクリートと鉄筋との応力の計算式は、下のようになります。
 . . . . . . . . (8)
. . . . . . . . (8)
式-1に示したkは許容応力を基にした計算式でした。式-7のkは、表現が異なりますが、本質的な性質は同じです。つまり、コンクリートと鉄筋の応力の比によって決まります。この意味は中立軸の相対的な位置が変わることで応力の比が変わることです。pが増加すればkも増加します。そのため、抵抗モーメントはコンクリートの許容応力の方で制限されます。逆にpを小さく設定すれば、抵抗モーメントは鉄筋の許容応力の方で決まります。